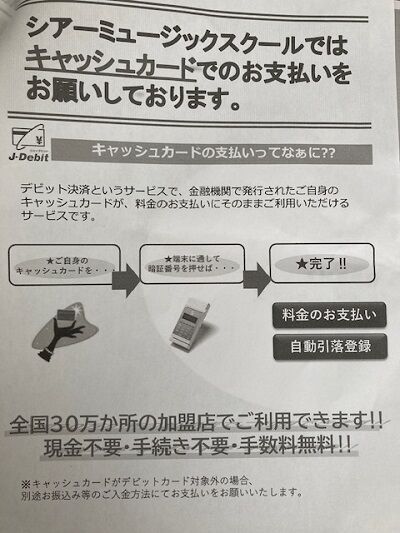コロナ、インフルが我が家の周りでもちらほら出ています。
秋なのにインフルかぁ・・・。コロナと両方かかる人もいるっていうし、子どもにとって感染症は天敵だぁ!
子どもの病気は、ほんとに生活が大変になっちゃうので、できれば避けたいのですが、免疫の量の違い?学校という場所柄?すぐもらってきちゃいます。
息子の学校ではインフルもコロナの子も出ているようで、もらってきても仕方ないな~と思っていたのですが、先にもらってきたのは娘でした。
学校で早退した子がいたらしいのですが、その日の夜には喉が痛いと言い出し、次の朝には熱が38度出ていました。
これはコロナかインフルかどちらだろう?と発熱外来の予約を取りました。
ここ数年、コロナのせいで発熱の度に病院を探すのが大変になっていました。病院の発熱患者に対する応対がなんだか嫌だったのですが、嫌だなって思うところを避けて、発熱の度に違う病院にぶつかっていってたら、発熱外来と、普通の病気と分けている病院が一番対応してもらえるのがわかったので、すぐにその病院へ予約を入れました。
↓うつる病気は個人病院より大きめ病院の方がいいのかな?ってお話です。
予約時間に行くと、「外で待っていて、電話で受付を呼んでください」とあらかじめ言われていたので、電話で受付の方に病院へ到着した旨を伝えます。
問診表と診察券と保険証を渡したら、娘は検査と診察に連れていかれて、「私は外で待っていてください」と、言われました。
以前ここにかかった時は、駐車場でPCR検査を行っていたのですが、駐車場ではなくて、病院の一番端っこの部屋で診察と検査をするようになっていました。
部屋で検査、診察してもらえるようになってる~
5類になったから?
しかし、付き人の私は外で待たなければならないってことで、1時間弱待ってました。
患者は中に入れるのに、付き添いはなんで外?
電話で、お子さんは何歳ですか?と聞かれたのですが、こういう事だからか~って思いました。一人で診察できないとダメって事?病院の診察って、結構駆け引き必要と私は思ったりします。
いままで息子や私の病気で、病院いっぱい行ったけど、無用では?と思われる薬を出す先生とか、横柄な先生とか、手荒に患者を扱う看護師さんとか、嫌な目にもいっぱいあったので、ちょっと心配でした。
HSPの娘にできるかな~![]()
ドキドキ、そわそわ待っていると、娘が看護師さんに連れられて帰ってきました。
看護師さんの話だと、抗原検査は陰性で、インフルが陽性。診断結果はインフルエンザA型でした。薬は薬局の人が持ってきてくれるので診察代だけのお支払い。
会計は800円でした。
保険3割負担ありがとう。
コロナだったらもっと高かったかも。
診察デビューが急に来てびっくり。
でも一人での診察できてよかった
高校生になると、病院行くのに、親が付き添い、した方がいいのか、逆にしない方がいいのか、すごく迷う。
以前歯医者に娘の付き添いで行った時も、娘がついて来いって言うので、ついて行ったら、やっぱり私、いらんかったようで、先生も看護師さんも、説明全部娘にしてた。
もう病院行く時は、一人で行ってもらった方がいいのかな?
娘的には、
何かわかんない事言われたら、どうしたらいいか困るも~ん![]()
夕方に薬局の人が薬を持ってきてくれて、もらったのはタミフルでした。

薬の説明は、持ってきてくれた人の携帯電話で、薬局の薬剤師の方に電話を家の前でかけて、つながったら電話を渡されて薬の説明を受けました。
発熱外来が、5類になって、変な方向に進化しているのに驚きです。ここまで非接触いるのかなぁ?
どこの病院もこんな感じ?この病院ならではの事情があるのかな?
でも、発熱して、診察断られたり、なんでうち選んだの?と言われた事件は、トラウマとなって、消えそうにないので、普通に診察してくれるだけでありがたいです。発熱して次の日には37度代に下がり、タミフル飲んで2日くらいおとなしくしていたら、鼻水以外はもう平常通りな感じでした。発症日を0日として、5日休みと学校からはお達しがあり、コロナとインフルダブル流行の今って、この後コロナかかったら、また休まないといけないよね
昔はインフルエンザ、普通の風邪より大変的な位置づけの病気だったけど、コロナの登場で、インフルでよかった~感があります。インフルエンザの方が治りやすい気もしています。
コロナは治りが遅い感じがするの私だけ?
感染症におびえずに暮らすのには、免疫力上げるしかないのかな・・・
スポンサードリンク