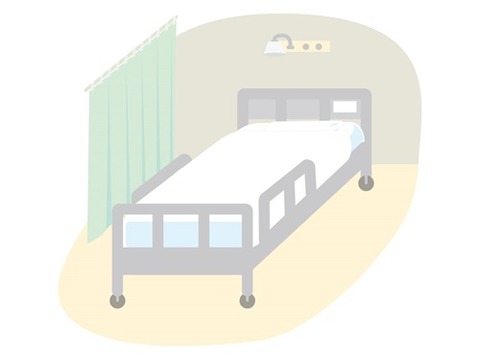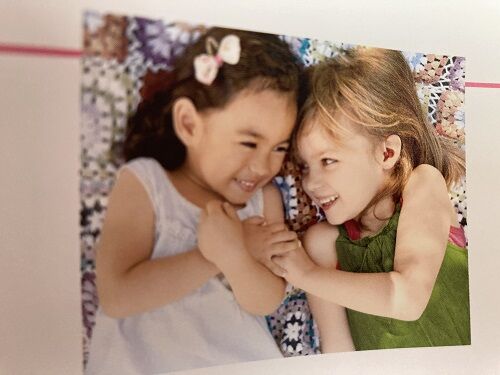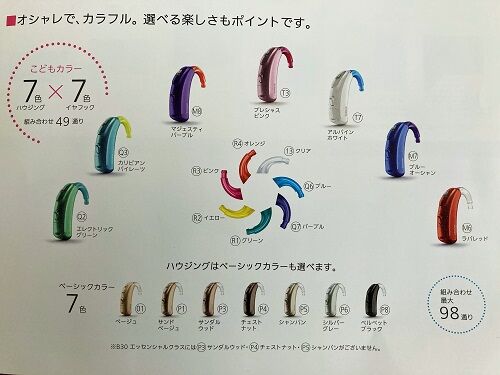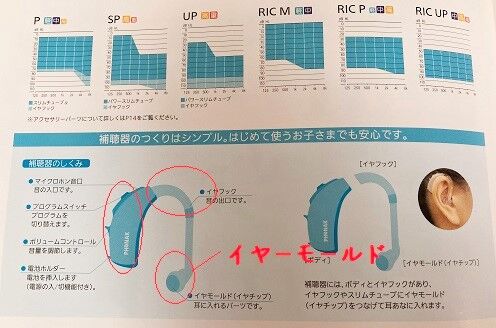クリスマス前、短期入所施設と契約しました。
家族にもしもがあった時に、ちょっとでも預かってくれるところがあると助かるので、探していたところ、障害児相談支援事業所の人に紹介してもらって見学に行って、契約の運びとなりました。
福祉型と医療型というタイプがあるそう。
契約には、放課後等デイサービスを利用する時のように受給者証が必要です。我が家では放課後等デイサービスを利用する際に、短期入所の受給者証も毎年一緒に申請しています。
毎年、デイ利用と短期入所利用をするかどうか書類が送られてきてて、利用するにチェックを入れて送り返してる。
申請して受給者証がもらえれば利用することができます。申請の際、日数も設定しないといけなかったのですが、我が家では7日にしました。家庭によっては長く申請しているところもあるのかも。短期入所施設は他にも契約したところがあるのですが、今度契約したところは、「宿泊施設」って感じ。以前に契約したところは、障がい者施設でした。
かなり前から探していて、2軒ほど見学に行ったのですが、どちらも障がい者施設で、そこでずっと暮らしている人がいて、そんな中で短期に受け入れができる枠がある、という形になっていました。
なので、ずっと利用している人が優先で、なかなか予約がとれないそう。よっぽとじゃないと利用させてもらないけど、もしもの時に心配なので、1つの障がい者施設との契約をしました。
契約はしたけど、もしもの時ってあんまりなくて、利用はあきらめていたのですが、今回紹介してもらったところは、宿泊のみの提供をしてくれているところでした。
もしものための慣らし宿泊をしたかったのですが、慣らしでは緊急性がないんだよね![]() 今度は慣らし宿泊しやすいかな?
今度は慣らし宿泊しやすいかな?
今回契約したところは、比較的新しくできたところみたいで、とてもきれいでした。建物の中に部屋が9部屋くらいあって、個室と2人部屋がありました。部屋の中にはテレビがありました。DVDも見られるそう。部屋はベッドの部屋と布団の部屋がありました。
↓部屋の中に布団ORベッドと、テレビが置いてあるだけの部屋でした。
おもちゃなんかはなかったです。障がい者施設は生活の場だからか、おもちゃとか本とか遊べるものがあったなぁ
おもちゃ持ってきてもいいとは言われたけど、あまり大げさな物は持ち込むと他の子達への影響もあるので、注意が必要のようでした。
うちの息子が利用する場合、ずっとDVDかYouTube見てろって感じになっちゃうな・・・
風呂は介助が必要な人用のお風呂と介助なしでも入れる人用がありました。リビングには大きなテレビもありました。利用の際、1泊2日(朝食、夕食、風呂つき)で1300円ということでした。
利用した場合の1日の流れは、
15時くらいから受け入れ開始▶️風呂▶️夕食▶️先に入れなかった人は夕食後風呂▶️自室ですごす
という風になっているそう。
自室での時間が長い~![]()
息子は一人で過ごす時間があまりない。
自分でできることが少ないので、常にだれかに見守られながら過ごすことになってしまっています。
こりゃいかん、なんとかせねば・・・
うちの息子、短期入所施設すら利用できないかも。
私や家族の者が入院とかになったらえらいこっちゃになっちゃう
うちはこれから「葬」ラッシュにもなりそうなので、準備しとかなきゃ、私動けん![]()
今まで、母親と同じ部屋で寝ていました。高校生になって、続き部屋の別々の部屋に寝るという形をとったのですが、布団同士が少し距離あるだけで、同じ空間で寝ている感じでした。
ダウン症児の息子だからか、筋肉量が少なくて?自分で温まれなくて、寒い日には私の布団に入ってきてた。あまり寒いと鼻水がたくさん出るようになって耳だれも多くなる。身体的にも夜は見守りが必要でした。
高校生になって、だいぶ身体ができてきたのか、寒い日も布団で一人で寝れるようになってきました。電気毛布は必須だけど・・・
ショートステイのために、去年の12月から、2階の個部屋で一人で寝るをやってきたのですが、3日目くらいから自分で勝手に部屋に行くようになりました。
親と一緒の空間に寝るの、もういやだったのかも
でもまだ自室で1人で過ごすというのができてない
私も息子が離れると、大丈夫かな?とめちゃくちゃ心配になるんで、これ、問題だよね
大丈夫と、心から息子を信頼できるように、今は別々の部屋で過ごせることを目標に頑張んなきゃ
契約の運びとなってから言われたのですが、「今は予約がすぐいっぱいになってしまう」のだとか。
え~?ここも?
放課後等デイサービスの利用と一緒で、毎月、月初めまでに次の月の利用を申し込むようなやり方なんだそうだけど、すぐうまってしまうらしいです。障がい者施設よりも受け入れ数多いのかな?と思ったけど、受け入れ部屋数多くてもニーズが多すぎて、まにあってない感じ?
定期的に利用していかないと、慣らしにならないんだけどな
親もいつまでも若くなく、いつまでそばにいてやれるかわからない。
親亡き後にスムーズに一人でもやっていけるようにしとかないと、と思ってるんだけどな。
お世話がまわってきた人たちにも、すごく迷惑がかかってしまうので、なんとか障がい児用のショートステイ先増やしてほしいんだけどな・・・。しかし、今のこの世の中じゃ無理じゃろうな・・・
スポンサードリンク